ご挨拶

大久保工務店は、創業60年の地域密着の工務店です。
祖父が鳶職人からスタートし、2代目の父の代では工場、マンション、学校の体育館などの公共工事にも進出しました。
なんでも作ることができる会社になった代わりに、以前は知らず知らずのうちに特徴のない家をつくる会社になっていたと思います。
しかし、3代目の私がゼネコンを退職し入社してからは、自然素材を用いて本物の価値、長く愛着を感じることができる家にこだわって家づくりをしております。
代表取締役 大久保 篤
宿命の3代目
私の祖父は、とび職から出発し、工務店を創業しました。少年時代の父の家庭は貧しく、父は夜学に通って、高校を卒業しましたが、すぐに祖父に呼び戻され、実家の手伝いをすることになりました。
そして、私は、生まれながらにして、大久保工務店の3代目と決まっていました。
私が少年時代に住んでいた家は、1階が木材の加工場、2階が住居という作りになっていましたから、子供の頃の私にとっては、加工場が格好の遊び場でした。
大工さんが削ったカンナ屑や、木片、ノコギリやノミといった大工さんの道具が沢山あって、物作りが好きな私にとっては、とても楽しい場所でした。
父は、会社を発展させることに忙しく、遊んでもらったという記憶が、あまりありません。しかし、職人さんたちが、随分と可愛がってくれて、よく遊んでくれました。
たまに大工さんの真似事をして、危なっかしいことをすると、叱ってくれたりもしました。
私には、いつも優しい職人さんたちも、仕事となると頑固で、父も、自分より年上の職人達を指揮することに苦労している様子が、子供心にも察することが出来ました。
「お前も相手の立場になって、人と付き合うようにしろよ」
「職人達に気持ち良く、心を込めて仕事をしてもらい、初めて良い家が出来る。そうじゃないと、お客さんに申し訳ない。引き渡せない。一生の付き合いなんだから」
それが、父の口癖でした。
子供心にも、大人になったら、自分が跡を継いで、皆をまとめなきゃとボンヤリと思っていました。
父が経営する工務店も、木造住宅だけではなく、徐々に鉄筋コンクリート造や、鉄骨造、公共工事なども請け負うようになって行きました。

社長 大久保 篤
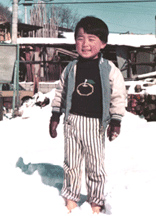
生まれながら、3代目
運命に逆らって、国際ビジネスマンの道?
高校生になった頃、父からこう言われました。
「高校か大学を出たら、地元の同業で、うちの会社よりも少し規模の大きな会社で修業し、数年後に戻って来い」
しかし、思春期の私は、祖父や父のように地元だけではなく、もっと広い世界を見てみたいと思うようになりました。
大きい会社に入って、出来れば、日本中、世界中を舞台に仕事をしてみたいと思ったのです。そして、大学を卒業してからは、海外にも進出している大手ゼネコンに就職しました。
少年時代から、木材や職人さん達に囲まれて育ったこともあって、物作りに対する憧れを抱いていたのです。
「広い世界で勝負したい。家には、戻ってこないつもりでいて欲しい」
父には、そう宣言して、社会に出ました。
思っていた通り、現場は日本中にあり、造るものの規模も違いました。念願が叶い、日本全国、そして、海外は、香港、サハリンと渡り歩きました。
夢に描いていた通りの人生でした。
外国人を相手に、あちこちと飛び回り、大きな仕事をする。言葉や環境、商習慣の違いなどで苦労することもありましたが、それも含めて、海外で働いている自分に満足していたのです。
自分のことを国際派ビジネスマンだと思っていました。
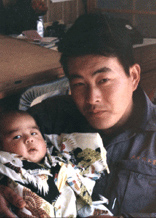
若いころの父と、私

サハリンにも勤務
原点回帰、本当の物づくり
しかし、華々しく活躍する中で、徐々に何か違和感を感じるようになってきました。子供の頃に思い描いていた「物づくりの喜び」がないのです。
ゼネコンで相手にするお客様と言えば、大手不動産などの企業、国などの役所でした。父が経営する工務店のように、一般ユーザーさんではありません。
汗水流して働いている職人さん達も、2次、3次、4次といった下請けの人達です。サラリーマンですから、転勤もしますし、担当も、営業、設計、工事監理と細分化されていました。
現場が完成すれば、お客さんとも、職人さん達との付き合いも、それで終わりです。メンテナンスの仕事も、後任の人が担当を引き継ぎます。
サハリンから帰国し、管理部門に配属された私は、「今のままでいいのか?」「これが、本当に自分が望んだ物づくりなのか?」
そんなことを考えて、心の中で葛藤が始まりました。
そんな時、妻から、「お父さんの会社のこと、どうするつもり?」と言われたのです。
妻は、結婚後、実家の工務店の手伝いをしていました。
だから、私以上に父の気持ちに気がつくことが出来たのだと思います。
「お父さん、本音では戻って来て欲しいんだよ」
「見てると、なんだか可哀そうなんだよね」
妻に、そう言われました。
私も、前から頭の片隅に気にはなっていました。しかし、「家には戻らない」と宣言して、大手ゼネコンに就職することを決めたのだから、今さら、跡を継ぐとは言い出せませんでした。
すると、「これ読んでみて!」と、父が書いた「自分史」という手記でした。
私は、それを読んで、涙が止まらず、父の苦労と、喜びが手に取るように分かり、小さなこだわりは捨てて、父の跡を継いで、3代目の工務店社長になることを決意したのです。
父の手記とは、こんな内容でした
下請け仕事ばかりでなく元請がしたい。お客さんと面と向かって直接仕事がしたいと思い、建築士の資格を取った。そのことを中学の恩師である守屋先生に報告すると、大変喜ばれ二人だけの宴席まで設けて頂いた。
その帰り途で言われたことに驚いた。
「大久保、俺の家を建てろ。お前にしてやれることはこのくらいしかない。」
うれしくて涙が出た。この家が我が社の自社物件第一号である。
自分はもちろん、大工をはじめ職人達も誠心誠意、心を込めて先生の家を建てた。先生はお亡くなりになり、今は娘さんが家を引き継がれ築40年以上になるが今でも現存し、これまでずっとメンテをさせて頂いている。
お客様に、感謝される仕事。自分の仕事は、これだ!
そう強く思いました。
誇り高い職人さん達がいて、お客様の満足する姿があって、一生付き合える関係が出来て、初めて自分も満足する。その繰り返しが、自分に係った人たちへの恩返しになると思ったのです。
すぐに父と相談し、自分の想いを話し、3代目を継ぐ後継者として、大久保工務店に入社を決めました。
 父の恩師、守屋先生
父の恩師、守屋先生順風万帆ではありませんでした
後継者とはいっても、1から修行し直すつもりで、現場監督として現場のゴミ広いから始めました。
私が子供の頃よく遊んでくれていた大工の棟梁も、厳しく、私を指導してくれました。
しかし、私が知っていた頃の大久保工務店と違って、仕事量も減っているように感じました。また、売り上げも建築の仕事よりも、土木工事のほうが、多くなっていました。
私の給料も、ゼネコン時代の半分でした。
「なんとかしなきゃ」と思う私は、「家の価格」を安くしようと安直に考え、資材価格を抑えた企画型住宅で盛り返そうと考えました。
大手資材メーカーのカタログを見て、手頃な価格の工業化製品を組み合わせただけのものでした。
しかし、棟梁が引退する時に言われました。
 3代目を継ぎました
3代目を継ぎました棟梁の言葉「逃げられねえんだぜ」
「俺は会社が決めたことに口出す立場じゃないけどさ。自分の目で探してきた資材なの? 長く使えるの? お客さんに責任持てんの? マンションとかさ、年に何百棟も家を建ててる大きい会社と俺ら違うでしょ。お客さんはそれで満足すんのかな?」
「あんたの親父さんはさ、お客さんに気を使って、俺らにも気を配ってやってきたよ。」
「修繕に行ってもお客さんが安心した顔じゃねえとな。」
「不具合があってもよ、逃げられねえんだぜ。」
頭を殴られたような衝撃を受けました。
いつも、寡黙に仕事をしてくれている棟梁が、本質的な問題点を指摘してくれたのです。
私は、3代目の後継者として焦るあまり、大切なことを見失っていたのです。
・造り手がプライドある仕事をして
・お客様が満足して
・会社=自分が満足して
のサイクル。一生責任をもってお客様とお付き合いすること。
それが、私が大久保工務店を継ぐと決意した時の「創業の想い」でした。
それを忘れていたのです。
 棟梁の本気を引き継ぎました
棟梁の本気を引き継ぎました本物を求めて「めっけもんになる」
それからの私は、価格が安いというだけで資材選びをすることを止めました。自分が納得のいく物を適正価格で提供するために、会社は小さくても、高品質な資材を作っている資材会社や貿易会社を調べ、時には、現地に行って、製造工程を確認したりもしました。
サンプルを取り寄せて、無垢材の収縮を確認したり、塗り壁材のひび割れ等を確認したりといったことを徹底してやるようになりました。
その「掘り出し物」探しは、今でも続けています。
自分が納得いくものを使うようになると、デザイン性が向上し、職人達も、イキイキとしていると感じるようになりました。
お客さんの笑顔も感じられるようになりました。
そして、私は、建築中の建物が、まるで愛娘のように感じるようになりました。
あるお客様に新築の建物を引き渡す時に、
「手塩にかけた娘をお渡しするような気持ちでさびしいです。今後ともよろしくお願いします。」と申し上げましたら、
「その気持ちが嬉しいです。本当にありがとうございました。いつでも遊びに来て下さい。」と、素晴らしい笑顔で言って頂け、私は泣きそうになってしまいました。
私が本当にやりたかったのは、こんな仕事なんです。
その後、点検でお伺いした時も、
「同時期に家を建てた友達に家をうらやましがられた。本物を使って良かった。大久保さんは、めっけもんだった。」と言って頂け、やっぱり、やったことは分かって頂けるんだ、伝わるんだと思ったのです。
私は、二度と、価格が安いだけの家は造りません。
そして、お客様から「めっけもんだね」と言われる工務店経営をしたいと思っています。
 本物の家を作り始めました
本物の家を作り始めました追伸
私は、「家なんて、どこに頼んでも一緒でしょ」と勘違いされている方に、ブランド力も営業力もない地域密着の工務店だからこそ作れる本物の家の価値をお伝えとしたいと思っています。
「八王子で、高性能なパッシブデザインの自然素材の家をつくっていく」ことが目標です。
そして、「本当に、いい家だね」と、友達がうなるほど自慢してくれる家づくりをしたいと思っています。
こんな大久保工務店の家づくりに関心がある方は、お問い合わせください。
